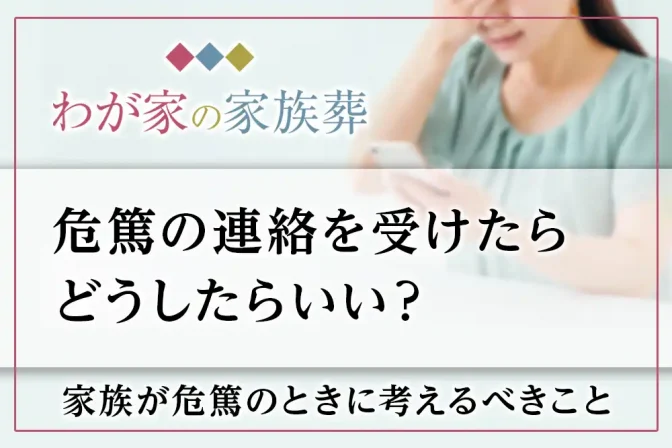
記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
大切な人が危篤だと病院から連絡を受けたら、行わなければならないことが多々あります。しかし精神的に大きなショックを受けているなかで、やるべきことを整理してスムーズに対応することは困難でしょう。そのためこの記事では、身内の方が危篤だと連絡を受けた際に対応すべきことや、亡くなった後に対応すべきことについて解説します。危篤・逝去に関する記事一覧は下記よりご確認ください。
【危篤/逝去について記事一覧】
「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
ドライアイスを20~30%以上値上げ
ドライアイス価格高騰により値上げを致します。
生前相談で
50,000円割引
危篤とは、病気や怪我で死の危機に瀕し、回復の見込みがないと医師が判断した状態です。医師が「脈拍(心拍)」「呼吸」「血圧」「体温」など、患者のバイタルをチェックし、危篤を宣言します。危篤状態だとしても、すぐに逝去するとは限りませんし、小康状態(しょうこうじょうたい)が続くケースもあります。また、医師に危篤と宣言された後に、回復するケースもあります。危篤を宣言された場合は、臨終を想定し準備をする必要があります。
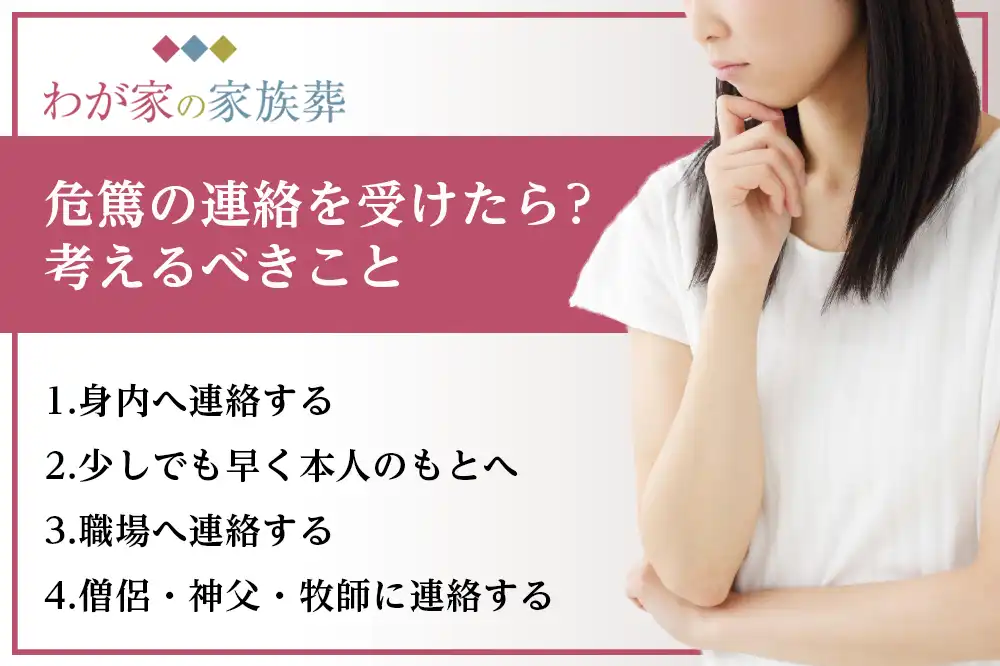
危篤の連絡が来て、焦らずにいることは困難なことでしょう。しかし危篤状態になって数時間で亡くなる場合もあれば、 1週間以上危険な状態が続くケースもあります。そのため、大変な状況ではありますが一旦落ち着き、やるべきことを整理しておくことが 重要です。基本的な対応すべきことは「身内へ連絡する」「少しでも早く本人のもとへ」「会社・職場へ連絡する」「僧侶・神父・牧師に連絡する」の4つです。危篤の連絡が来た際にはまず深く深呼吸をして、落ち着いて行動しましょう。
身内への連絡は、一報を受けたら最初に行っておきたいことです。 一人でも多くの親族に連絡を行い、駆けつけられるようにするのが大切でしょう。 親族の範囲に決まりはありませんが、一般的には3親等までの親族とその配偶者が多いといえます。 3親等とは、本人を基準に、本人の配偶者、兄弟姉妹、子、孫、ひ孫、おい・姪となります。
ただし上記を基本とし、親しい友人・知人にも連絡するとよいでしょう。 また、遠方に住んでいる人に関しては、葬儀の日程を決めた際に連絡するとの考え方もあります。 遠方の場合、臨終に間に合うように駆けつけられない可能性があるためです。 連絡をする際にはできるだけ冷静になり、相手をパニックにさせないことが重要でしょう。 電話が最も確実ですが、連絡がつかない場合はメールやメッセージなどでも問題ありません。
少しでも早く本人のもとへ駆けつけることも、重要なことです。本人と話ができる最期の時間になるかもしれないためです。 声かけできる状態ではない可能性もありますが、臨終に立ち会う覚悟を決めるためにも、早期に駆けつけることは重要でしょう。 さらに、本人が生きている間に伝えたいことを聞いたり、こちらの思いを伝えたりすることもできるかもしれません。 声をかける際には、決してネガティブなことはいわないことが大切です。
親族に加えて、自分自身の会社・勤務先への連絡も重要です。今後、忌引き休暇を取得する可能性もあるためです。 危篤状態が数日続く場合は、仕事への影響を考慮して定期的に連絡を入れることが求められます。上司や同僚に連絡をして 理解を得ておいた方が、今後の状況に合わせた対応を依頼しやすくなるはずでしょう。会社・職場への説明にあたっては、 医師の言葉を用いると理解を得やすいでしょう。
宗教者である僧侶・神父・牧師への連絡も、行っておくべきです。その後の対応を考えると、 ここで連絡をしておいた方がスムーズなためです。菩提寺があれば、連絡をしておきます。 また、キリスト教の場合は臨終前の儀式を行うため可能な限り早期に神父・牧師に連絡することが大切です。
危篤状態の人にかける言葉は、前向きで本人が安心できるような言葉をかけましょう。注意点や、どんな言葉をかけたら良いか、例文を紹介しながら解説します。
危篤状態の人に言葉をかける理由は、本人に最後まで希望を持ち続けてもらうためです。危篤状態だとしても、声掛けに反応することもあるそうです。言葉をかけて、反応がなかったとしても、家族や親しい人の気配を感じ、安心できます。その安心感から、孤独感や死への恐怖が緩和されるといわれています。
危篤状態の人にかける言葉は、和やかに前向きな、安心できる言葉を選んで声掛けしましょう。楽しかった思い出話を語りかけ、ポジティブな雰囲気をつくるのも良いでしょう。
危篤状態の人にかける言葉の注意点として、「死」を連想させる言葉を避けましょう。また、無理に励ます言葉も使わないようにしましょう。既に頑張っている状況では、本人を追い詰めてしまうことになるかもしれません。穏やかで、本人が安心できる言葉を選ぶことが重要です。

もし身内の方が亡くなったら、「死亡診断書を受け取る」「死亡届を7日以内に提出する」「埋火葬許可申請書を申請する」 「葬式について考える」の4項目の対応を進めることが大切です。
やらなくてはならないことは想像以上にあり、故人を失った悲しみのなかで対応するのは大変です。 不安なことが少しでもあれば、葬儀社に連絡して最大限サポートしてもらうのも重要でしょう。
死亡診断書の受け取りは、まず行うべきことの一つです。身内が病気で亡くなると、主治医より「死亡診断書」が発行されます。 死亡診断書がないとその後のさまざまな手続きを進められないため、忘れずに受け取り紛失しないようにしなくてはなりません。 ただし、死亡診断書を役所へ提出すると返却してもらえないため、コピーを複数枚取って対応することが大切です。 また、病気ではなく事故や事件などで亡くなった場合は、警察に連絡されて検視を受けた後、「死体検案書」を 作成してもらうことになります。
故人の死亡届は、死亡を知った日から7日以内、国外であれば3か月以内に提出しなくてはなりません。 理由なく提出が遅れると、戸籍法により5万円以下の過料を科せられることもあるため、早期の対応が重要です。 死亡診断書(死体検案書)と一つになっている「死亡届」に必要事項を記入し、後ほど説明する「家相許可申請書」と ともに提出します。提出先は、以下のいずれかを管轄する役所です。
葬儀者に依頼することで代行してくれるため、やはり早期に葬儀社へ連絡するのが重要でしょう。
埋火葬許可申請所は、死亡届の提出と同時に申請することが一般的です。自治体によって名称が異なりますが、 埋火葬許可申請書とは埋葬・火葬を行う許可を得るための書類です。申請後に受け取れる許可証がなければ、 遺体を火葬・埋葬することができません。
葬式についても、身内が亡くなった際には考えなくてはいけません。葬儀社は複数あるため、各社の料金やプランを 比較しながら考えることが大切です。まずお伝えしたいのが、葬儀費用は「総額がいくらになるか」で選んでください。10万円以下の 格安表記されている葬儀プランは、「火葬料」が別途追加費用となる場合が多くあります。また、ご遺体の安置日数に制限があり、それを超えると、 日数分の安置費用やドライアイスの費用が、別途追加費用として加算されてしまいます。わが家の家族葬では「安置日数無制限で安置料・ドライアイス無料」での表示価格でご提供しているため、お見積り後に追加費用が発生することが一切ありません。また、葬儀場の使用料も含まれた表示価格となっております。 下記、わが家の家族葬の4つの料金プランです。「家族葬|火葬式プラン」「家族葬|納棺式プラン」「家族葬|1日葬プラン」「家族葬|2日葬プラン」のそれぞれの、家族葬プランの費用と流れをご紹介します。
火葬式は通夜や告別式を省略して火葬のみを行う葬儀のことで、直葬(ちょくそう)と呼ぶこともあります。葬儀の参列者は、家族や親戚や生前故人様と親しくしていた関係者のみを招いて行われることがほとんどで、故人とのお別れは火葬炉の前で行われます。
【火葬式プランの費用と流れ】
納棺式とは、故人様の身支度を整えて棺へと納める儀式をいいます。ご家族様が故人様とふれあうお別れ式です。故人様の愛用品や趣味の品物、大好きだった食べ物等の副葬品を、お花と一緒に納めることが多いです。
【納棺式プランの費用と流れ】
1日葬は通夜を行わず、葬儀・告別式・火葬を1日で行う形式の葬儀です。一般的な葬儀では通夜と葬儀・告別式・火葬を2日間に分けて行いますが、1日葬では通夜を行いません。通夜ぶるまいの「飲食代」がかからない分、費用が安くなります。
【1日葬プランの費用と流れ】
2日葬は一般葬と同様に、僧侶などの宗教者立ち合いのもとで通夜と告別式で2日間にわたり行われ、葬儀の日程や進行も一般葬と同じ順序であることが多いです。通夜は一般会葬者を招いて行い、葬儀は近親者で行うなど、2日間で行うことで様々な送り方がご提案可能です。
【2日葬プランの費用と流れ】
人が亡くなった際には、納棺前までにご遺体に対し、死後処置が施されます。もしも、身内が亡くなった際に、後悔なくお見送りが出来るよう、事前に知っておくことが大切です。死後処置として、エンゼルケア・エンバーミング・湯灌の3種類についてお伝えします。関連記事もあわせてご参照ください。
エンゼルケアとは、逝去後から納棺前までに行う死後処置のことです。明確な定義はありませんが、死化粧を施すまでを含んで、エンゼルケアと呼ばれます。エンゼルケアは、逝去時ケアと呼ばれることもあるようです。故人を少しでも生前に近い姿になるように整えるための処置全般のことを指しており、医療的知識が必要な処置を含んだものになります。これに対し、エンゼルケアに含まれる「死化粧」という処置は、ご家族や葬儀社、納棺師などが行える処置です。エンゼルケアは、身だしなみを整え、故人の尊厳を守り、少しでもきれいな姿で見送ってあげたいというご家族の想いに寄り添うための処置です。病院で亡くなった際には、医師の死亡宣告の後、直ちに行われます。基本的には事前に説明がありますが、ご家族が気が付かないうちに済んでいたというケースもあるようですので、心配な場合は確認しておきましょう。
エンバーミングとは、ご遺体に殺菌消毒・防腐や修復をし、顔の表情や姿を生前に近い状態に整え、自然な状態で長期保全することを目的とした「遺体衛生保全」の処置や技術・技法のことです。 日本語では「遺体衛生保全」や「死体防腐処理」などと訳されています。 そして衛生面のほかに、お顔を元気だった頃に近づけ、ご家族のグリーフケア(悲嘆ケア)としての側面もあります。 ドライアイスや保冷庫が不用で、自然な状態でのご安置が可能となります。エンゼルケアや湯灌が表面的な処置であるのに対し、エンバーミングは処置が体内にまで及ぶことが特徴です。土葬文化のある海外では古来より行われている処置です。日本では、阪神大震災以降からエンバーミング処置を希望するご家族が増加し、普及してきています。
湯灌とは、故人の体をぬるま湯で洗い清める、納棺前の儀式のことです。かつては親族の手で行われ、成仏の手助けとして儀式的な意味合いが強いものでした。湯灌には濡らしたタオルで体を拭く略式の湯灌と、実際に浴槽に故人を寝かせて洗い流す湯かんがあり、後者の湯灌は専門業者や葬儀社に手配をしなければならず、費用もかかります。病院や介護施設で亡くなった場合は、エンゼルケアの一環として「清拭」をしてくれるので、それで済ませてしまうケースも増えています。
危篤の連絡を受けたら、やっておくべきことが多数あります。気が動転してしまい辛いものではありますが、 事前にやるべきことを整理しておき、まずは深呼吸をして対応していきましょう。身内の方が亡くなった後にも、 対応すべきことや期限までに行うべき手続きはあります。ご遺族やその代表の方だけで背負うと大きな負担になってしまうため、 無理をせずまずは葬儀社に相談するのが大切です。危篤・逝去についての関連記事も併せてご参照ください。
最後に、なぜ家族葬で「小さいわが家のお葬式(わが家の家族葬)」が選ばれているのか、ご紹介したいと思います。
他社との違いは、次の3項目です。1.総額費用が安い。追加費用一切なし。2.安置室完備。3.一貫して自社対応。
一般的に、「火葬料」や「式場使用料」が別途追加費用として必要だったり、ドライアイスや安置日数に制限が設けられていますので、比較する際は注意が必要です。
小さいわが家のお葬式(わが家の家族葬)では、対象の施設でのご葬儀の場合に「安置日数無制限で安置料・ドライアイス無料」での表示価格でご提供しているため、お見積り後に追加費用が発生することが一切ありません。
経済的な心配をせず、お別れに集中していただける環境をご提供させていただいております。また、年々増加している「エンバーミング」も、
自社対応可能な葬儀社であることが特徴です。下記ぺージでも、イラストと合わせてご紹介しています。
【家族葬で選ばれる理由】
【エンバーミングとは】
資料請求やお問合せは
メールフォームをご利用下さい。
お急ぎの方はお電話から
記事のカテゴリー
お急ぎの方は今すぐお電話ください。
生前相談で割引適応!