
記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
故人のご遺骨を納骨・埋葬するには「埋葬許可証」が必要です。しかし、手続きの最中に「どこで受け取るの?」「火葬許可証と何が違うの?」「なくしてしまったらどうする?」といった疑問を抱く方もいるでしょう。
本記事では、埋葬許可証の基本的な知識から、火葬許可証との違い、取得の流れ、万が一紛失した場合の対処法までを丁寧に解説します。葬儀後の大切な手続きをスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
ドライアイスを20~30%以上値上げ
ドライアイス価格高騰により値上げを致します。
生前相談で
割引適応!
埋葬許可証は、ご遺骨を正式に埋葬・納骨するために必要となる公的な書類です。ここではまず、この書類の定義と役割について整理し、火葬許可証との違いも押さえておきましょう。
埋葬許可証とは、故人の遺骨をお墓や納骨堂に納めるために必要な書類です。納骨時に、墓地や霊園の管理者に提出する義務があります。
発行主体は市区町村で、火葬が終わった後に、火葬許可証に「火葬済」の証明印が押されることで埋葬許可証となります。納骨という最終的な弔いのステップで欠かせない、法的根拠のある書類です。
埋葬許可証と混同されやすいのが「火葬許可証」です。実際には、多くの自治体で「火葬許可証」が火葬場での執行印を押された後、そのまま「埋葬許可証」として使われます。
つまり、名称は同じでも、火葬前は「火葬許可証」、火葬後には「埋葬許可証」としての効力を持つようになります。自治体によっては書式に若干の違いがあるものの、基本的な扱いに大きな差はありません。
この書類が必要なのは、無許可の埋葬や分骨を防ぎ、公衆衛生や社会秩序を保つためです。また遺骨の所有や保管・移動に関する法的な証明にもなります。
例えば改葬(別の墓地への引っ越し)の際にも提出が求められるなど、一度きりではなく、長期にわたって必要になるケースもあるため、大切に保管しておきましょう。
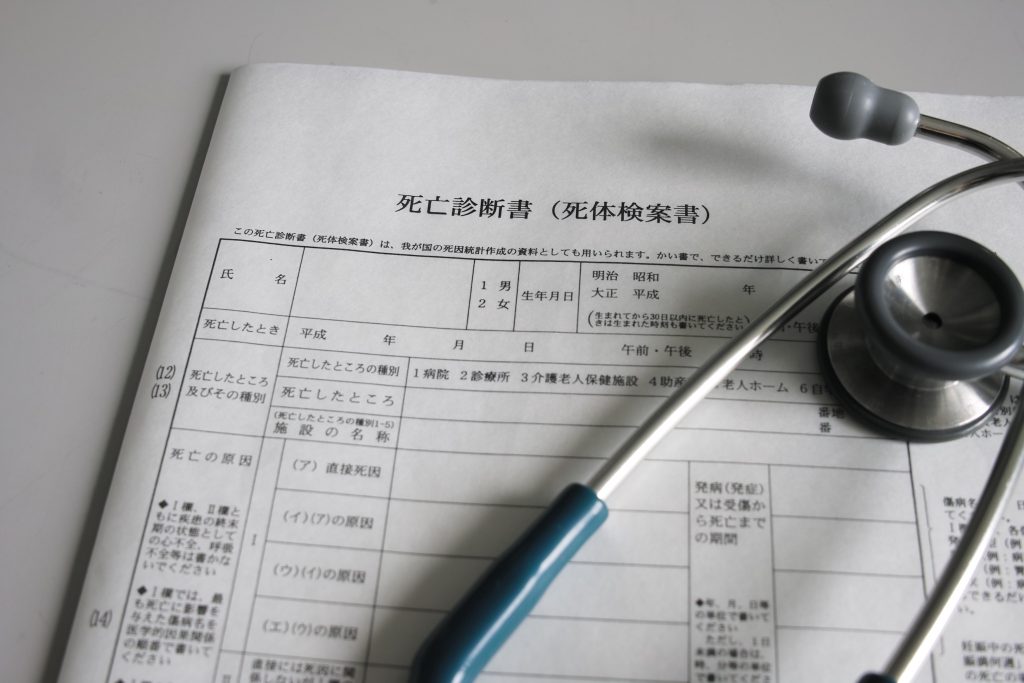
埋葬許可証を手にするまでには、いくつかの段階的な手続きがあります。以下のステップに沿って、順を追って確認しましょう。
最初のステップは、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ることです。この書類は、火葬や埋葬の一連の手続きを開始するために欠かせません。
故人が亡くなった後、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。これは法律で定められた義務であり、死亡の事実を公的に届け出るための重要な手続きです。届出先は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの役場となります。提出時には、医師が作成した死亡診断書と一体になった死亡届と、届出人の印鑑などが必要です。
この手続きが完了することで、火葬許可証の交付や以後の葬儀・納骨の準備が正式に進められるようになります。遺族自身が提出することも可能ですが、葬儀社が代行するケースも多いため、不安がある場合は相談すると良いでしょう。死亡届の提出は、葬儀後の流れを滞りなく進めるための第一歩です。
死亡届を提出すると同時に、市区町村役場へ火葬許可申請書を提出する必要があります。この申請が受理されると、火葬の実施に必要な「火葬許可証」が交付されます。火葬許可証がないと火葬を行うことができないため、葬儀のスケジュールに合わせて速やかに申請を済ませることが大切です。火葬許可証の交付は通常即日で行われますが、窓口の混雑状況などによっては時間がかかる場合もあります。
火葬許可証は、火葬場に提出する他、火葬後には埋葬許可証としても使用されるため、大切に保管しておきましょう。
火葬当日には、あらかじめ発行された火葬許可証を、火葬場の管理事務所に提出します。火葬許可証がないと、原則として火葬を実施することはできませんので、当日に忘れず持参しましょう。
火葬が終了し、収骨(お骨上げ)が終わると、火葬場から「火葬執行済」の印が押された火葬許可証が返却されます。この印が押された時点で、その書類は「埋葬許可証」としての効力を持つようになります。
この埋葬許可証は、後日の納骨時に墓地や霊園、納骨堂の管理者へ提出するための重要な書類です。通常は、骨壺とともに桐箱などに収められ、葬儀社から遺族へ引き渡されます。納骨の際に必要になるため、火葬後は紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
埋葬許可証は、故人の遺骨を納骨する際に必要となる公的書類です。納骨式の当日、または事前に管理事務所へ提出を求められるのが一般的で、提出が確認できないと納骨を断られることもあるため、忘れずに準備しておきましょう。
また遺骨の一部を分けて複数箇所に納める「分骨」を行う際には、分骨証明書の発行に当たって埋葬許可証の提示が求められるケースがあります。さらに、現在の墓地から別の場所へ遺骨を移す「改葬」の手続きを行う際にも、元の埋葬地で埋葬許可証の提出が必要になる場合があります。いずれのケースでも、あらかじめ提出先の施設や自治体に必要書類を確認しておくと良いでしょう。

万が一、埋葬許可証を紛失してしまった場合でも、再発行が可能です。以下にその方法と注意点を解説します。
埋葬許可証を紛失した場合は、原則として火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行の申請ができます。
ただし、火葬から長期間(おおむね5年以上)が経過している場合には、先に火葬場から「火葬証明書」または「火葬執行証明書」を取得し、それを役場に提出する必要があるケースもあります。再発行に必要な書類は自治体によって異なりますが、故人の氏名・死亡日・火葬日が分かる情報、申請者の本人確認書類、場合によっては申請理由を記した書類などが求められるのが一般的です。
窓口対応の他、郵送や代理人による申請が認められることもあるため、事前に該当する市区町村の役場に確認するのが良いです。葬儀社に依頼していた場合は、手続きを代行してもらえることもあるため、相談してみると良いでしょう。
再発行を希望する際は、即日で対応してもらえる自治体もある一方で、数日かかる場合もあるため、余裕を持って申請することが大切です。
また申請者が死亡届を提出した本人であるか、故人とどのような関係にあるかによって、手続きの手間や必要書類が異なる場合があります。埋葬や改葬などの予定がある場合には、提出の期限に間に合うよう、紛失に気づいた段階で速やかに役所へ相談・申請することが望まれます。
埋葬許可証は、故人のご遺骨を正式に納骨するために欠かせない重要書類です。火葬許可証との違いや、取得までの流れ、提出先や再発行の方法を理解しておくことで、納骨に関する手続きをスムーズに進められます。
「小さいわが家のお葬式」では、こうした複雑な書類の取得・管理もサポートし、遺族の不安や負担を軽減することを大切にしています。葬儀後の手続きで不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
資料請求やお問合せは
メールフォームをご利用下さい。
お急ぎの方はお電話から
記事のカテゴリー
お急ぎの方は今すぐお電話ください。
生前相談で割引適応!