
記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
身近な人が亡くなった際に「訃報をどのように伝えるべきか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。いざというときに「いつ、誰に、どのように伝えるのか」を事前に知っておけると、当日急に連絡しなければならない事態になったとしても、スムーズに伝えられるでしょう。
本記事では、訃報の伝え方やマナーを知りたい方に向けて、訃報の意味や葬儀案内との違い、正しい伝え方と基本的なマナー、伝え方の例文などを解説します。訃報を受け取ったときの対応や気を付けるべき注意点なども解説しているので参考にしてください。
「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
ドライアイスを20~30%以上値上げ
ドライアイス価格高騰により値上げを致します。
生前相談で
割引適応!
まずは、訃報の詳しい意味や葬儀案内との違いを解説します。
訃報とは、身内や親しい人の死去を知らせることを意味します。日本では、訃報を伝えるのは故人の家族や親族で、訃報の内容を作成してから生前に親しかった友人や勤務先などに伝えるのが一般的な流れです。訃報を伝える範囲は故人の交友関係の親密度によっても異なります。近年では身内だけで葬儀を行う家族葬を選ぶケースが増えており、訃報の内容もごく限られた範囲の人にのみ連絡する形が主流になりつつあります。
訃報は単に身近な人が死去したことを伝えるための事務的な連絡ではありません。訃報を知らせたい相手や伝えるべき内容を、慎重に検討した上で伝えることが重要です。訃報を伝える主な手段として、電話やメールなどが挙げられます。
訃報と葬儀案内はどちらも人が亡くなったことを伝える連絡であるものの、それぞれ伝える内容が異なります。訃報は遺族が関係者に対して、身近な人が亡くなったことを知らせるための連絡を意味します。訃報の内容は、故人の名前や亡くなった日時などを伝えるのが一般的です。一方の葬儀案内は遺族から葬儀に参列してほしい人に対して、通夜や葬儀の日程、会場、宗派など、葬儀の参列に必要な情報を伝えるための連絡を指します。
訃報を伝えてから葬儀案内を出すのが基本的な流れです。訃報は故人が亡くなったタイミングで伝え、葬儀案内は葬儀の日程が決まってから知らせるのがマナーです。ただし、葬儀までの日程が短い場合や遠方の人にいち早く葬儀案内を届けたい場合は、訃報と葬儀案内を同時に伝えるケースもあります。
訃報は、基本的なマナーを守って伝えることが大切です。故人の死去を知らせる連絡であるため、伝えるべき相手に漏れがないよう注意しましょう。本章では、訃報の基本マナーを解説します。
訃報は故人が生前時に親しかった人だけではなく、故人と関係する全ての人に伝える必要があります。まず頭に思い浮かぶのは親族や故人の親しい友人、知人などでしょう。他には、勤務先や仕事関係者、自治会や町内会の関係者にも訃報を伝えます。ただし、訃報は優先順位に基づいて伝えるのがマナーです。一般的な訃報の優先順位は以下の通りです。
訃報を最初に伝えるべき相手は家族で、次に親族、友人、仕事関係者または学校関係者、自治会関係者の順番で訃報を伝えます。ケースによっては信仰する宗教宗派の関係者に訃報を伝えるケースも存在します。
近年は家族葬を選択するケースも多く、葬儀の詳細が決まってから訃報を伝える形が主流になりつつあります。葬儀への参列が必要な親族にはできるだけ早いタイミングで訃報を伝えることが大切です。特に遠方に住む親族がいる場合は故人が亡くなった直後に電話で訃報を伝える必要があります。葬儀案内は、日程や会場などが決まったタイミングで知らせれば、安心して葬儀に参列する準備ができるでしょう。
故人の勤務先や仕事関係者、自治会の関係者には葬儀の詳細が確定したタイミングで訃報と葬儀案内を伝えてもマナー違反にはなりません。ただし、葬儀当日や直前に伝えるのはマナーに違反するため、相手の住む場所も考えて訃報を伝えましょう。
訃報を伝える主な手段は電話やメール、手紙・ハガキがあります。どの連絡手段でも伝える内容に誤りがないかを確認してから伝えましょう。
電話は訃報を直接かつ迅速に伝えられる連絡手段です。訃報と一緒に葬儀の詳細を伝える際は相手にメモの準備を促し、聞き取りやすいようにゆっくり話すことを心掛けます。また連絡漏れがないよう、連絡先リストを作成してから電話をかけましょう。
メールは訃報を複数人にまとめて伝えられるメリットがあります。ただし、目上の人や一定の礼儀が求められる相手にメールで訃報を伝えると失礼になるため、他の連絡方法を選びましょう。
手紙やハガキで訃報を伝える方法もあります。葬儀に参列してほしい場合は相手が余裕を持って参列できるように、準備期間も考慮して早めに送ることが大切です。郵送した旨を電話で伝えておくと良いです。

訃報で伝えるべき内容は故人の情報や亡くなった日時、死因などです。訃報と併せて葬儀の詳細も伝える場合は、日時や会場などの情報も忘れずに伝えましょう。本章では、訃報で伝えるべき内容を解説します。
訃報連絡では故人の氏名や年齢、住所などの情報を伝える必要があります。訃報の連絡者が連絡を受ける相手と面識がない場合は、連絡者と故人との間柄に触れてから詳しい内容を伝えると、相手も安心して受け入れられるでしょう。葬儀の詳細を伝える際は喪主の氏名も伝えておきます。
喪主を務める人の氏名を伝える理由は、葬儀に関する問い合わせ先を明確にするためです。葬儀の欠席を伝える場合、喪主や遺族に伝えるのがマナーです。また喪主の名前は葬儀に参列できず、弔電や香典を斎場へ送る場合に必要になります。訃報は故人の死去を知らせるだけではなく、受ける相手にも配慮しながら必要な内容をしっかり伝えましょう。
訃報連絡では、故人が亡くなった日時や死因にも軽く触れます。故人が亡くなった経緯や死因は、訃報を受け取った人が弔電を送るときや葬儀で挨拶する際の内容にも反映されるため、死因を伝えられる場合は事故や病気など、簡潔に説明しておきます。
ただし、死因は遺族や訃報を受ける相手にとってデリケートな話題のため、無理に伝えなくてもマナー違反にはなりません。伝える内容が生々しかったり伝え方が悪くて誤解を招いたりすると、訃報を受け取る相手の心を傷つける恐れがあります。そのため、全ての人に故人の死因や亡くなった経緯を詳細に伝える必要はありません。訃報連絡で故人の死因を伝えるかどうかは遺族間で話し合って決めましょう。
訃報連絡の際に葬儀の日程や会場などの詳細が確定している場合は、訃報と一緒に葬儀に関する情報も伝えます。伝えるべき主な内容は以下の通りです。
通夜や葬儀に参列する人の服装や故人の見送り方など、事前に知らせるべき内容がある場合は訃報連絡と併せて伝えます。訃報を連絡する時点で葬儀の予定が決まっていない場合は、葬儀の日程や会場などの情報は後日連絡する旨を伝えておきましょう。家族葬のように一般の参列を制限する形式を取る場合や、香典・供花などの受け取りを断る場合は、訃報連絡のタイミングでその旨を伝えておきましょう。
メールや手紙・ハガキで伝える場合は一般的な定型文を活用できますが、電話で訃報を伝える場合は何をどう伝えればいいのか分からない人もいるでしょう。本章では、連絡手段別に訃報の例文を紹介します。
訃報を電話で伝える際は、間違った情報を伝えたり言い忘れたりしないように連絡すべき内容をメモにまとめておくことが大切です。まずは親族や友人に伝える場合の例文を紹介します。
例文1
(相手の名前)さん、ご無沙汰しております。(故人の名前)の長男の(自分の名前)です。実は、入院中の父が(亡くなった日時)に息を引き取りました。今は(病院名)に安置されていて、今日引き取りに行き、通夜・葬儀までは自宅で安置します。通夜は(開始日時)に、(斎場名)で行います。詳細は追ってご報告しますので、何かありましたら(連絡先)にご連絡ください。
例文2
いつも父がお世話になっております。(故人の名前)の長男の(自分の名前)と申します。闘病中の父が昨夜息を引き取りました。葬儀は親族のみで行うため、失礼ではありますがご厚意は辞退させていただきます。ご迷惑おかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
メールでは句読点を打ってもマナー違反になりません。読みやすさを意識し、まとめられる情報は箇条書きにしましょう。
件名:【訃報】(故人の名前)儀(続柄)
(宛名)様
令和〇年〇月〇日、父(故人の名前)が永眠いたしましたことを、ここにご報告させていただきます。生前は多大なご厚情を賜り、深く感謝申し上げます。
通夜・葬儀は仏式にて執り行う予定で、詳細は下記の通りです。
・日時:(葬儀の開始日時)
・会場:(葬儀場所)
・喪主:(喪主の名前)
・連絡先:(喪主の連絡先)
ご多忙中とは存じますが、ご列席賜りますようお願い申し上げます。
件名:急逝のお知らせ
(宛名)様
(亡くなった日時) 父(故人の名前)が病気により他界しました
生前は大変お世話になりましたこと 父に代わって厚く御礼申し上げます
通夜・葬儀は以下の通り執り行う予定です
・日時:(葬儀の開始日時)
・会場:(葬儀場所)
・喪主:(喪主の名前)
・連絡先:(喪主の連絡先)
手紙・ハガキでは句読点を打たずに、縦書きで記載するのがマナーです。葬儀終了後に訃報を伝える場合に、手紙やハガキを送付します。例文は以下の通りです。
父(故人の名前)儀 去る(亡くなった年月日)に 病気により永眠いたしましたことをここに謹んでご通知申し上げます
生前は多大なご厚誼を賜り 感謝申し上げます
葬儀は故人の希望により 親族のみで(葬儀日時)に滞りなく相済ませました
(送付年月日)
(郵便番号、住所) 喪主 (喪主の名前)
父(故人の名前)は(亡くなった年月日) 他界いたしました
みなさまに謹んでお知らせ申し上げます
なお 葬儀は(葬儀日時)に滞りなく相済ませました
ここに 生前中のご厚情に深く感謝し 通知申し上げます
(送付年月日)
(郵便番号、住所) 喪主 (喪主の名前)
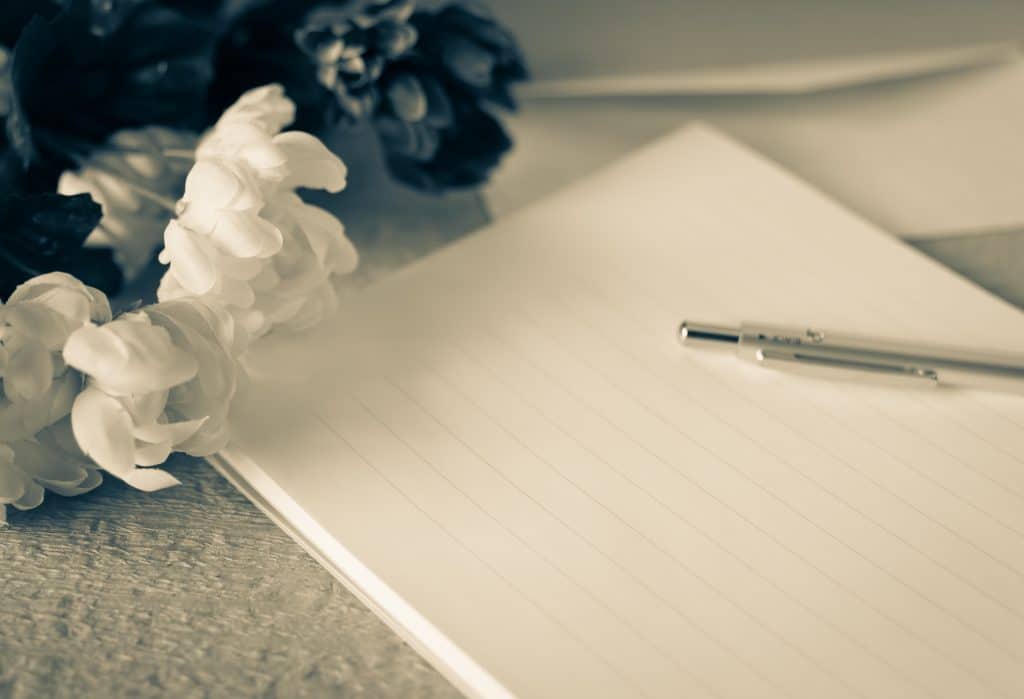
訃報を連絡するだけではなく、受けることもあるでしょう。訃報は突然知らされるケースが多いため、受けた場合の対応方法を確認しておくことで適切な対応ができます。
身内の訃報は他の家族や親族、病院から受けるケースが一般的です。訃報の知らせを聞いたときは、亡くなったのが身近な人であるほどショックで混乱する可能性があります。特に家族が亡くなった場合は通夜や葬儀の準備をはじめ、死後の手続きをしなければなりません。例えば、家族が亡くなった場合は遺体の安置場所や搬送方法、通夜や葬儀を依頼する葬儀社などを決める必要があります。全ての準備や手続きを一人で行うのは大きな負担になるため、他の家族や親族と協力して進めることが大切です。
遠方に住んでいる場合は通夜や葬儀に出席できるように、勤務先や関係各所と相談してスケジュールを調整しておきましょう。出席できる日程を事前に家族と共有することで、遠方からでも通夜や葬儀に参列しやすくなります。
身内以外の訃報を受けた場合は、使用する言葉に注意する必要があります。特に気を付けたいのは、忌み言葉を避けることです。身内なら忌み言葉を使用しても大きな問題にはなりませんが、身内以外の人に使うと遺族を不快な気持ちにする恐れがあります。訃報への返信で忌み言葉を使用することはマナー違反に当たります。忌み言葉の主な例は以下の通りです。
特に訃報を電話で受け取った場合は、突然の連絡で思いついた言葉をそのまま口にしやすいため、万が一に備えて使用を控えるべき忌み言葉を把握しておきましょう。
訃報を受けた側は、返信のタイミングや返信時のマナーを考慮する必要があります。本章では、訃報を受けた際の基本的なマナーや気を付けるべき注意点を解説します。マナーや注意点を知ることで、訃報連絡が来た際にも慌てずに受けられるでしょう。
訃報連絡を受け取った場合は、できるだけ早い返信を心掛けることが大切です。訃報を受け取ってからすぐに返信する理由は、返信が遅れることで喪主や遺族に心配をかけたり不安にさせたりするのを避けるためです。メールや手紙・ハガキによる訃報連絡を受けた場合は、早朝や深夜を避けて日中または翌日に返信します。遅くても故人が亡くなった日時から7日以内の初七日までに返信するのがマナーです。
万が一、訃報に気づかず返信が遅れた場合はお悔やみの言葉だけではなく、返信が遅れたことに対するお詫びの一言を添えます。通夜や葬儀に参列できない場合や初七日を過ぎてから訃報を知った場合は、日を改めて弔問します。遺族が弔問を望まなかったり弔問に訪れるのが難しかったりする場合は、お悔やみの手紙を送りましょう。
訃報をはじめ弔事の文章には句読点を使用しないのがマナーです。訃報の返信で句読点を使わない理由は大きく分けて2点あります。一つは毛筆で書かれた書状に句読点が使われていないことです。もう一つの理由は、句読点が文章を区切るために使用されることから、「切れる」や「終わる」などの言葉を連想させてしまうことです。弔事では「葬儀が滞りなく済みますように」という祈りを込めて、句読点を使わないようにしてください。
ただし、メールで句読点を省くと読みにくくなるため、句読点を使っても許容範囲とされています。メールで句読点を使わない場合は、言い回しに注意したり適度な改行を入れたりすると良いでしょう。
訃報連絡の返信は、遺族の心情に配慮して簡潔な内容にしましょう。遺族は故人を失ったショックを受けている上に、葬儀の準備や手続きで心身が疲労しているため、大きな負担をかけないように細心の注意を図らなければなりません。生前中に故人と親しかった場合でも、長文の返信は遺族の負担になってしまう恐れがあります。遺族の負担を軽減するポイントは以下です。
時候の挨拶は形式的な印象を与えかねないため、省略しましょう。また故人の死因や亡くなるまでの経緯を知りたくても、遺族が触れてこない限りはこちらから尋ねないようにするのがマナーです。返信の最後に返信不要の一言を添え、遺族の負担を軽減しましょう。
訃報は単に故人の死を伝えるだけの連絡ではなく、故人や遺族にとって特別な意味を持つ儀礼です。訃報を伝える側は相手やタイミング、連絡手段によって伝え方を変える必要があります。一方で、訃報を受け取る側は故人へ敬意を払うとともに、遺族の心情に配慮した対応が求められます。
どちらの立場になっても、訃報の基本的なマナーや例文を参考にしながら、状況に合わせた丁寧な対応を心掛けましょう。相手や状況に合わせて訃報を正しく伝えることは故人の意思を尊重しつつ、生前に親交があった相手との信頼を守るために欠かせない心遣いです。
小さいわが家のお葬式では費用をできるだけ抑えながら、故人を弔えるプランを提案しています。葬儀の事前相談を承っていますので、ご不安な点があれば、まずはぜひご相談ください。
資料請求やお問合せは
メールフォームをご利用下さい。
お急ぎの方はお電話から
記事のカテゴリー
お急ぎの方は今すぐお電話ください。
生前相談で割引適応!